2020.11.29
記憶をめぐる物語を2冊
すごく久しぶりに読書日記をアップすることに。今年度はコロナウィルスの本格化とともにいきなり4月に10日程度微熱が続き、過剰に外出することに恐怖を感じだしたあたりから常にストレスがかかっていて、仕事用(研究用)の書籍はまだしも、趣味の時間として本を読めていなかったのだけど、年末を間近にしてようやくここまで回復したのかという実感。以下、記憶をめぐる書籍を2冊。
▼
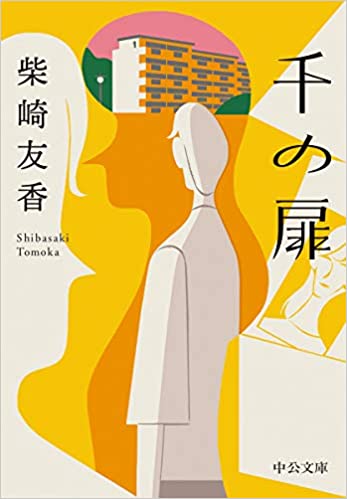
1冊目は柴崎友香の『千の扉』。世間的には東出さんの件で『寝ても覚めても』が代表作になってしまっているのかもしれないが、僕は『わたしがいなかった街で』で恐らく最初に手を取って、文庫化されたものは5割ぐらい読んでいる感じなのかな。僕がメディアと空間の問題を研究者としてはこの10年扱っていて、人文地理学なども多少カバーしているからだと思うのだけれども、彼女から一貫して感じるのは記憶の問題で、その記憶が場所と身体に根ざしているという感じが何とも言えず好き。読んだ人、もしくは映画を見た人(私は見ていない。濱口さんにも少し悪い)は分かると思うけど、『寝ても覚めても』も記憶をめぐる物語でもある。
これはとってつけたような感想だけど、彼女が自身が育った関西の時間の流れを、印象的に描ける(生き生きととは違う気がする)のはまああるだろうと思うのだけれども、東京の「ザ・戦後」しかも、戦争そのものに必要以上の過重をかけない描き方は、本当に記憶を書くことが上手い人なんだなとしみじみ感じた。概要はamazonででも見てくれという感じですが、昭和の団地をめぐるある種の集合的記憶が描かれています。あと、自分と近い年齢だからというのもあると思うのですが、40前後の年齢に差し掛かった男女が、「家族であること」とどう向き合うかという物語でもある。実は、僕はこの二つ目のテーマについてはこの小説ではかなりシンパシーを感じた。
▼

2冊目は早瀬耕の『プラネタリウムの外側』。まず、装丁綺麗。『未必のマクベス』は書店で何度も手に取って買うか迷っていたのだけれども、今回も手に取ると横に平積みになっていたので購入。この4,5年AIと人間の関係性を描くようなSFを定期的に読み続けているのだけれども、普通に新潮や講談社の文庫本として出しても読める、文学作品としてまとまっている。記述も綺麗だし、表現として分かりづらいと思うけど、輪郭の柔らかい作品。構成としては短編集というしかないのだと思うけど、一話一話はそれぞれきちっとつながっていて、一つの長編作品としての読後感がある。
主人公は、北大の大学院の二人の若手研究者なのだが、それぞれが何らかの欠落感を感じて生きている。多分、唯一ネアカ的に描かれているのは主人公の指導教員。その欠落感は、おもに愛情と記憶に関わるもので、この二つのテーマに依拠したAI(を用いたサービス)とのやりとりのなかで、主人公およびそれぞれの章のキーキャラクターに心情の変化が生まれていく。それぞれの章に出てくるキーキャラクターはかなり内容的には強めの心情表現になってもおかしくない人はいるのだけれども、実際にはこのぐらいのレベルで心が揺れるのではないかという線で澄んだ描かれ方がされているのに好感を持った。
この2冊の前に読んだのが、山田悠介の『僕はロボットごしの君に恋をする』だったのだが、山田作品初めて読み元々美しさや深さをさほど求めておらず、授業のネタぐらいになればと思って読んだが、エンターテイメント性の高い小説としても僕はダメだった。『プラネタリウムの外側』は2年ぐらいに分けて、1話40分程度で京アニあたりにアニメーション化して欲しい(子安武人や大原さやかみたいなオール大人の魅力声優陣で)、こちらはすでにアニメーション化されるようだがちょっと無理かもしれない。
検索
アーカイヴ
- 2025年3月
- 2024年1月
- 2023年4月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年4月
- 2021年12月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年3月
- 2020年11月
- 2020年6月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2019年10月
- 2018年6月
- 2018年2月
- 2017年11月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2015年12月
- 2015年6月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年8月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月